直木賞受賞作、カフェーの帰り道(嶋津輝/東京創元社)。帯の「百年前のわたしたちの物語」という言葉以外、前情報ゼロで挑んだ。
直木賞作品で、しかも受賞直後。レビューも書評も世の中に溢れているはずだ。けれど私は、それらを一切踏まずに本編へ入った。結果的にそれがよかった。先入観がないぶん、物語の“味”がそのまま舌に乗った。
カフェではなくカフェー、この響きで──帯を読まなかったとしても──少し昔の話だということは想像がつく。ふだんならあまり手にすることのない時代のものだ。だからか最初は読み進めるのに少しばかり、時間を要した気がする。ふだんの1.2倍くらいはページを捲るスピードが遅かったのではないだろうか。
5作の連作短編集だが、時代背景の違いがあるからか、すべての行動や時間軸がゆっくり流れているように感じられた。1分も1時間も1日も1ヶ月も今と昔では同じスピードのはずだ。インターネットはもちろん電話やテレビがない。あるのは新聞と手紙。情報が速く届かない世界では、出来事の輪郭が急がない。そのせいか物語自体が、おおらかに見えた。戦争の前後という背景を思うと、忙しない日々もあったのだろうに——こちらだけが勝手に息を急がせている気がして、少し申し訳なくなる。
すべての話がカフェーに繋がり、それでいて登場人物が少しずつ絡み合っているのは、なんだか青山美智子さん味がある。しんどくなる部分はあっても、なんだか最後はわかりあえるし”ほぼ”いい感じ。そんなお話の連続は心地よい。読むスピードもだんだん上がってきた。最後の2作は一気に読んだ。
なによりも心に残ったのは、ある章の最後だ。ラストに大どんでん返しがあったわけではない。けれど、ページを捲った先、たった「1文」──行数にして2行──で息を呑んだ。 文字の大きさもフォントも変わっていない。それなのに、漫画の見開きで「ドーン!」と描かれたような衝撃。この結末か──と、心を掴まれたのだ。
もしかしたら文字数の関係でたまたま、そのようなページ割りになっただけかもしれない。必然なのか偶然なのかはわからない。それでもこの編集(ページ割り)になったから、ここが一番心に残っている。
神編集なのか、たまたまなのか、こたえは文庫版で明らかになる(かもしれない)。










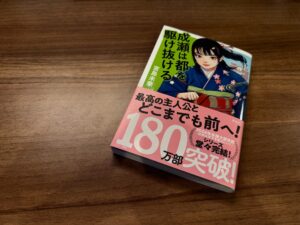
コメント