爆弾犯の娘(梶原阿貴/ブックマン社)を一気に読んだ。クリスマスツリー爆弾事件の犯人の娘が逃亡劇、そして人生を振り返る半生記と簡単に括れる話ではなかった。
ノンフィクションだからこそなのか脚本家の著者だからなのかはわからないけれども、「けっこう普通」だった。これは悪い意味ではない。いや、爆弾犯の娘という嘘偽りのないタイトルがそもそも派手という突っ込みはさておき、逃亡生活の中で描かれる学校生活なんかは、想像していたものよりも普通に思えたのだ。
もちろん著者本人や家族、そして犯人そのものは大変であり過酷で精神的に参ったりすることも多々あったはずだ。 ただ、ドラマチックな展開の連続というよりは、少し訳ありな家族の日常が淡々と描かれていた。大きい章のなかに小見出しがある構成だが、その一つ一つだけを切り取ってみるとそれはまるでエッセイだ。
だからなのか。重たいテーマであり暗い雰囲気が漂い、読者がしんどくなりページを捲る手を止めてしまう、といったことが少ないのではないか。一気読みとまではいかなかったけれどもわりかしサクサク読み進めることができ、想定したよりも速く読み終わった。とくに出頭からは速かった。ギアをぐいっと一段、二段と入れたようだ。
フィクション(小説)は往々にして派手なことが起こる。現実の世界でそんなに簡単に密室トリックにでくすことはない。じゃなくても「伏線」と呼ばれるようなことを仕掛けてあったりする。それがない。結果として「ここで出会った人が後にタッグを組む」といったことがあっても、設定上といった無理矢理感などまるでないし、「人生ってそういうことあるよね」の範囲内だ。そもそも著者の人生なんだけれども。
帯くらいしか前情報がなかったこの本の印象は時とともに変化した。「娘の独白」から「逃亡劇」「家族物語」「著者の半生記」そして最後は「社会問題」──正解か間違いかの二択ではないけれども、いろいろな面を持っている。どこが印象に残ったのかで、読者が抱く「テーマ」は変わってくるだろう。
作家は多くの人に読んでもらうことを夢見て、執筆するのだろうけれども、本来であれば重苦しく薄暗いテイストにでもできた爆弾犯の娘として生きていく(きた)ことを、恐らく敢えて深刻ではなく書いたのは多くの人に読んでもらいたいから、知ってもらいたいからなのではないだろうか。










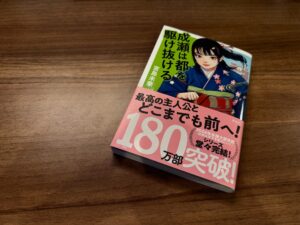
コメント