エピクロスの処方箋(夏川草介/水銀社)を読み終えた。前作であるスピノザの診察室(夏川草介/水銀社)を読んでいなくとも、話は理解できる。ただ、前作を読んでいたほうが、話に奥行き、あるいは立体感、もしくは手触り感が宿り、より一層作品の世界(観)を楽しめるのは確かだ。登場人物の繋がりや考え方、哲学が引き継がれているからだ。
時間とお金に余裕があるならば、前作(スピノザ)を読んでからこの本(エピクロス)を手に取るのをおすすめする。
問いかけが散りばめられている
医療の現場を舞台にした小説はとても多い。そして人気になるものも多数ある。古くは白い巨塔(山崎豊子/新潮社)、そして平成に入ってからはチーム・バチスタの栄光(海堂尊/宝島社)、最近では禁忌の子(山口未桜/東京創元社)。
ただスピノザ、エピクロスと続くこの2冊はそういったものと一線を画すと思う。なんというのだろうか。医療とはなにか、生と死とはなにか、生き方とはなにか、などいろいろな問いかけがなされている。物語は終始、答えを示すのではなく、問いを読者の前に差し出し続ける。もちろん作品の中で登場人物たちなりの答えは出てくるものもあるが、「1+1=2」のような正解では当然ない。
どれも正しく思えるし、それぞれの正義と正義がぶつかり合う。そこに悪はない。だからこそ無念さも胸に残るのである。わかりやすい悪がいて、「いやいや、それは流石にないだろう」と思えたらどんなに楽だっただろうか。そうならないからこそ作品として味わい深いのだろう。
そこで投げかけられる問いは、医療現場に限った話ではない。多少の置き換えをすれば、ぼくたちの日常にも通じることがたくさんあった。医療現場に身を置いていないぼくも小説を読みながら考えさせられた。問い詰めていくとそれは哲学だった。
読後感は哲学書
読書をしたというよりも、いくつかの哲学について考えさせられた、これが読了後の頭に浮かんだ感想だ。スピノザ、そしてエピクロスと哲学者の名前が題名になっているだけある。
ぼく自身、哲学に詳しくない。アリストテレスやカントにソクラテス、そしてプラトンと哲学者の名前は出てくる。でも実際どんな考え方だったのか、どういう時代背景があるのか、という前提知識(もしかしたら教養なのかもしれない)がまるでない。そこがあるともう少し深みが出たかもしれないと思うと、自分の知らなさに少し悔しくもなる。
こういった経験は哲学に限らずよくある。小説やドラマで「あ、これはこういう意味だな」と演出から気がつかず、放送終了後のネット記事や感想戦でそれとなく知ってしまうのだ。そのときの悔しさは絶望に近いものがある。もちろん気がつくこともある。だが、圧倒的に知らないことのほうが多い。世の中のことをすべて知ることはできないけれども、もう少し積み重ねていくことで、仕掛けにもう少し気がつくのではないだろうか。
もしかしたらスピノザやエピクロスについて、もう少し知っていれば夏川先生の違ったメッセージを受け取ることができたのかもしれない。










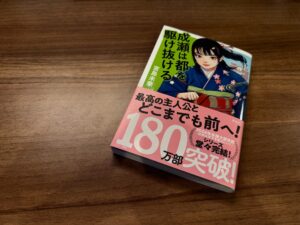
コメント